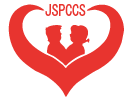症例1
症例
2歳男児
診断名
修正大血管転位症,心室中隔欠損症,WPW症候群
現病歴
在胎39週1日,体重3,110 gで出生.月齢1時にチアノーゼを伴う強直発作を契機に修正大血管転位症,心室中隔欠損症,動脈管開存症と診断された.造影CTにて肺動脈の圧排による気管狭窄を認め,チアノーゼ発作の原因と考えられた.生後1か月で心室中隔欠損閉鎖および動脈管結紮術,肺動脈吊上げ術が施行された.生後10か月時に発作性上室性頻拍を呈しWPW症候群と診断された.1歳時より解剖学的右室の機能不全が顕在化し,1歳4か月で大血管スイッチ,hemi-Mustard/bidirectional Glennによるone and a half ventricle repairおよび心房内クライオアブレーションが施行された.術後1年より労作時の息切れが出現し,定期外来受診時に低アルブミン血症および胸水貯留を認めたため精査加療目的に入院した.
併存疾患
なし
内服薬
アスピリン,ソタロール塩酸塩
入院時現症
身長80.5 cm,体重13.2 kg,脈拍100回/分,血圧84/48 mmHg,呼吸数20回/分,SpO2 94%(室内気下),右下肺野で呼吸音減弱,心音整,心雑音なし,腹部膨満なし,四肢に圧痕性浮腫あり.
入院時検査所見
血液:WBC 5,400/µL(Neutro 66.6%, Lym 23.7%, Eosino 4.3%),RBC 572×104/µL, Hb 15.3 g/dL, MCV 80.2 fL, Plt 25.8×104/µL, TP 3.9 g/dL, Alb 2.0 g/dL, CRP 0.05 mg/dL, IgG 50 mg/dL以下,BNP 10.7 pg/mL.尿蛋白:陰性.胸水:TP 0.3 g/dL, LDH 26 U/L, T-Cho 9 mg/dL.その他,血液学的検査および生化学的検査に異常なし.胸部単純X線検査:心胸郭比43%,肺野の透過性低下なし.心臓超音波検査:心収縮能正常.
入院後経過(Fig. 1)
99mTc消化管シンチグラフィーで回盲部に異常集積を認めPLEと診断した.また胸水は非乳糜であり,低アルブミン血症に続発したと考えられた.心臓カテーテル検査では下大静脈(inferior vena cava: IVC)baffle内に最小径3.6 mmの狭窄を認め,6 mmHgの圧較差を伴い,IVC圧は10 mmHgと上昇していた(Fig. 2).また,上大静脈(superior vena cava: SVC)圧と肺動脈圧はともに10 mmHgであり,Glenn吻合部に狭窄は認めなかった.アルブミン補充,利尿剤,プレドニゾロンを併用し,入院9日目に胸水は消失し,Alb値も3.5 mg/dLに上昇を認めたため入院17日目に退院した.その後PLE再燃やステロイド薬長期使用の副作用を懸念し,PLE発症2か月後に外科的にIVC baffle狭窄解除を施行した.術中所見ではbaffle内の冠静脈洞unroofing部位に肥厚組織を認め,これを切除し狭窄を解除した(Fig. 3).術後2か月でプレドニゾロンを終了し,術後1年の心臓カテーテル検査で狭窄解除部前後に圧較差を認めずIVC圧が4 mmHgに改善したことを確認した.その後5年の観察期間で再燃なく経過した.
症例2
症例
5歳男児
診断名
修正大血管転位症,心室中隔欠損症,肺動脈閉鎖症
現病歴
胎児期に心奇形を指摘された.在胎38週1日,体重2,703 gで出生し,修正大血管転位症,心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症と診断され,月齢1でBlalock–Taussig(BT)シャント術が施行された.その後,解剖学的右室の機能低下が顕在化したため,2歳時にSenning術とRastelli型手術によるダブルスイッチ術が施行された.その後,肺静脈還流路狭窄およびSVC baffle狭窄に対し,それぞれ2歳および3歳時に修復術が施行された.以後安定して経過していたが,5歳時に顔面浮腫,下痢および低アルブミン血症を認め,精査加療目的に入院した.
併存疾患
異所性心房頻拍,左横隔神経麻痺,気管支喘息
内服薬
ビソプロロールフマル酸塩,アミオダロン塩酸塩,フロセミド,モンテルカストナトリウム
入院時現症
身長102 cm,体重16.9 kg,脈拍85回/分,血圧90/50 mmHg,呼吸数20回/分,SpO2 100%(室内気下),呼吸音清,心音整,胸骨左縁第2肋間にて収縮期雑音を聴取,腹部膨満なし,肝脾腫なし,顔面浮腫あり,四肢浮腫なし.
入院時検査所見
血液:WBC 4,500/µL(Neutro 65.8%, Lym 19.2%, Eosino 4.2%),RBC 558×104/µL, Hb 15.4 g/dL, MCV 78.5 fL, Plt 23.1×104/µL, TP 4.4 g/dL, Alb 2.9 g/dL, CRP 0.02 mg/dL, IgG 132 mg/dL, BNP 27.5 pg/mL.尿蛋白:陰性.その他,血液学的検査および生化学的検査に異常なし.胸部単純X線検査:心胸郭比49%,肺野の透過性低下なし.心臓超音波検査:心収縮能正常.
入院後経過(Fig. 4)
便中α1-アンチトリプシンクリアランスの測定や99mTc消化管シンチグラフィーは未実施であったが,低アルブミン血症と下痢などの臨床症状,および他疾患の除外から,PLEと診断した4).入院と同時に,内科的治療の強化として脂肪制限食を導入し,静注利尿剤を併用した.入院3日目の心臓カテーテル検査ではSVC baffle内に最小径2.2 mmの狭窄を認め,5 mmHgの圧較差を伴い,SVC圧は10 mmHgと上昇していた(Fig. 5).IVC baffleに狭窄は認めず,IVC圧は7 mmHgと正常であった.SVC狭窄に対し経皮的血管形成術を施行し,最小径5.0 mm,圧較差1 mmHgに改善した.なお12 mm径のバルーンカテーテルによる拡張中に体血圧が低下し,拡張中の経胸壁超音波検査でSVC baffleに隣接する肺静脈還流路の閉塞を認めた.患者の年齢・体格も考慮し,ステント留置は見送られた.同治療後に静注薬を終了し入院11日目に退院した.前後して各症状は軽快し,発症1か月後の血清Alb値は4.5 mg/dLまで改善し,脂肪制限を解除した.その後2年間PLEの再燃なく経過している.
PLEは先天性心疾患領域においてFontan術後に経験されることが多く,その原因や治療法に関する報告もFontan術後の発症例について論じたものが大半を占める.しかしながらPLEは非Fontan術後にも経験され,その多くには血行動態的に修復すべき病変があり,それらを修復することでPLEの改善を得られることがある.心房内血流転換術後におけるPLEはその典型例であると言える.
これまで心房内血流転換術後遠隔期のbaffle狭窄発生率は0~20%と報告されており5–7),さらにbaffle狭窄が発生した場合においても,側副血行路が発達し圧上昇が軽減されるため,PLEの発症に至る例は稀だとする報告もある7).しかしながら本検討において,自験例を含め心房内血流転換術後のPLE例の大多数がbaffle狭窄を有し,またその解除後にPLEの寛解が多く報告された点からは,これらの狭窄による血行動態の悪化がPLEの主因になっていると考えられる.一方でFontan術後におけるPLEでは,中心静脈圧上昇の他にも低心拍出の関与や,血行動態以外では炎症の関与などが原因として論じられており,これら多因子が複合して発症にかかわることが推察される3).自験例においてPLE発症時点で明らかな心不全徴候は認めなかったが,2例とも修正大血管転位症であることを考慮すれば,心房内血流転換術前の体心室右室の収縮障害や,術後に存在する潜在的な心機能障害がPLE発症に影響を与えた可能性も完全には否定できない.またPLE発症への炎症の関与はステロイド薬が奏功する点により裏づけられるが,潜在的な全身性炎症のマーカーとして用いられる好中球/リンパ球比や血小板/リンパ球比の高値がFontan術後のリンパ管拡張やリンパ管新生と相関するという報告がある8).またFontan術後や収縮性心膜炎,腸リンパ管拡張症に続発するPLEにおいてCD4陽性T細胞の減少を主としたリンパ球減少を多く認めることも報告されており,これら免疫系の異常はPLEの背後にある炎症の反映とも考えられる9).自験例においてもリンパ球数は症例1で1,280/µL,症例2で864/µLと低値を示しており(年齢毎の基準値,症例1:3,000~9,500/µL,症例2:1,500~8,000/µL10)),潜在的な炎症が存在していた可能性がある.
また自験2例で狭窄部位がそれぞれSVCおよびIVCと対照的でありながら,2例ともPLEを発症した点は,その病態を考察するにあたり特筆に値する.Fontan術後PLEにおいて高い中心静脈圧は,門脈圧上昇や消化管の静脈うっ滞を引き起こし,リンパ流の抑制によるリンパ管圧の上昇が起こることでPLE発症の一因になっていると考えられている11).心房内血流転換術後のIVC狭窄例においても同様の機序でPLEを発症している可能性がある.一方で,reviewにおいて自験例の症例2を含む5例ではSVCの狭窄病変のみでPLEを発症しており,SVC圧上昇単独であってもPLE発症の誘因となることが示唆された.SVC圧上昇に伴うPLE発症例はGlenn術後の症例が報告されている12).先天性心疾患以外に目を移せば,SVC症候群や先天性胸管欠損など,胸管・リンパ管圧の上昇に伴うPLEの報告も存在する13, 14).自験例および文献からも因果関係の立証はなされていないが,SVC閉塞に続発する胸管圧上昇を介した腸管リンパ流うっ滞の関与の可能性が想起される.
さらに心房内血流転換術後PLEの治療に関して,自験例はそれぞれ外科手術およびカテーテル治療によるbaffle狭窄解除がPLE治療として有効であった.とくに症例2では,狭窄解除後速やかにPLEの寛解を得ることができた.またreviewにおいても,baffle狭窄解除が施行されたうち73%の症例でPLEに対する有効性が報告された.これは,Fontan術後のPLEにおいてFontanルート狭窄に対する治療介入後のPLE改善率が18~33%に留まるのに比して,高い有効率である15, 16).心房内血流転換術後のPLEにおいて,狭窄がある場合にその解除をすることで,Fontan術後のPLEよりも高い治療効果が期待できると考えられる.一方で11例中3例では狭窄解除後もPLEが遷延し,うち1例ではリンパ管造影検査で十二指腸へのリンパ漏出を認め,選択的リンパ管塞栓術を施行することでPLEが寛解した17).Fontan術後のPLEにおいてはPLE発症前に無症候性のリンパ異常が存在している可能性も考えられており11),心房内血流転換術後のPLEにおいても,狭窄解除で改善しない場合にはリンパ管造影検査等によるリンパ異常の検索が有用となる可能性がある.ただし本文献中の各例とも狭窄解除に並行して多種の内科的治療が併用された結果を見ており,狭窄解除の純粋な治療効果を測ることは困難である.また,観察期間についても一貫した定義はできておらず,長期的な予後については今後さらなる研究が必要である.