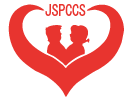14歳男性.身長121.9 cm,体重26.8 kg.両房室弁右室挿入,左室低形成,肺動脈閉鎖,動脈管開存に対して1か月時のBTシャント変法,10か月時の両方向性Glenn手術を経て,2歳時に18 mm expanded polytetrafluoroethylene(ePTFE)グラフトを用いたtotal cavopulmonary connection(TCPC)手術が行われた.5歳時に四肢浮腫,腹水貯留,下痢が出現し,PLEの診断となった.いったんは副腎皮質ステロイドが著効したものの,減薬や中止で再発を繰り返し,ステロイド依存状態となった.骨粗鬆症の合併により8歳時には胸腰椎圧迫骨折を発症した(Fig. 1).14歳時に撮像したCT(computed tomography)でTCPCの導管に石灰化を伴う屈曲と軽度の狭窄(最狭部断面積は正常部の41.2%)が指摘された(Fig. 2).
内服薬は以下の通りである.フロセミド20 mg,スピロノラクトン90 mg,ワーファリン1.6 mg,アスピリン50 mg,タダラフィル20 mg,イミダプリル1.4 mg,プレドニゾロン25 mg(隔日).
現症は血圧102/66 mmHg,脈拍数92回/分,経皮的酸素飽和度(SpO2)94%,呼吸音は清,心音はI, II音とも亢進減弱はなかった.肝下縁は季肋下3 cmまで大きく触知した.胸部単純X線では心胸郭比38%で肺野に異常所見なく胸水も認めなかった.ADLは自立しているが,ごく最近になってNHYA分類はII度程度へとわずかに進行した.
血液検査所見はWBC 8000/µL, HCT 46.9%,TP 5.2 g/dL, Alb 3.7 g/dL, AST 18 U/L, ALT 18 U/L, ALP 436 U/L, γ-GTP 37 U/L, T-BIL 1.23 mg/dL, K 3.1 mEq/L, BUN 5.8 mg/dL, CRE 0.35 mg/dL, BNP 8.19 pg/mL, IgG 110 mg/dLであった.
心電図は洞調律で特記すべき異常なく,QRS幅は0.07秒であった.
心臓超音波検査ではFAC(fractional area change)は54%と主心室収縮能は良好で房室弁逆流も僧帽弁より軽度認めるのみであった.経三尖弁血流のE/Aは1.3でE/e′は10以下であった.上下大静脈および心外導管内の血流は吸気呼気ともに順行性かつスムーズに流れており,Fontan循環に明らかな異常は認めなかった.
難治性PLEの原因評価と導管屈曲部の精査のため,心臓カテーテル検査が行われた.下大静脈造影では導管屈曲部の狭窄度は導管径の50%であった.肺動脈圧は17/15(平均15)mmHg,下大静脈圧は15/14(平均15)mmHgとやや高値であったが,屈曲部前後での引き抜き圧較差は0 mmHgであった.また,上下大静脈造影では明らかな側副血行路は認めず,導管屈曲部での造影剤の異常なpoolingも認めなかった.肺血管抵抗は1.57 unit·m2であった.右室拡張末期容積(right ventricular end-diastolic volume: RVEDV)は74.4 mL(Z score −0.41)と心拡大はなく,右室壁運動も良好で駆出率(ejection fraction: EF)は74%,心係数(cardiac index: CI)も2.59 L/min/m2と保たれていたが,拡張末期圧(right ventricular end-diastolic pressure RVEDP)14 mmHgと上昇を認めた.房室弁逆流はI度のみであった(Fig. 3).
導管屈曲部の狭窄率は50%を超え肝腫大の所見は認めるものの,圧較差はなく,PLEが寛解していれば下腿浮腫を含め狭窄に由来する自覚症状は乏しかったため,積極的な手術適応ではないと考えられた.ただし,この導管屈曲はPLE発症時点での指摘はなかったものの,現在の難治性PLEに対しては増悪因子としての関与は否定できないと考えられた.また,導管内に圧較差は認めなかったが,低圧系のFontan循環において狭窄の重症度の評価は圧較差のみでよいのか,側副血行路による下大静脈血流量低下が狭窄を過小評価させている可能性はないか,という点で議論の余地があった.そして中心静脈圧上昇の主因はRVEDPの上昇であると考えられたが,なぜRVEDPが上昇しているのか原因を特定することはできなかった.
そこで,屈曲した導管の交換を含めた治療方針の検討のため,4D flow MRIを施行した.多断層矢状断での3次元位相コントラスト法に加えて多断層矢状断でのSSFP(steady-state free procession)法によるシネ画像を撮影した.後解析には4D flow MRI血流解析ソフトウェアiT flow ver 6.01,(株式会社Cardio Flow Design, Tokyo, Japan)を用いた.上大静脈および下大静脈血流はそれぞれ1.16 L/min, 1.86 L/minであり十分な下大静脈血流があることが判明した.また明確な側副血行路は認めず,上下大静脈流量の和は心拍出量とほぼ同等であった.導管屈曲部での血流の加速は認めず最大流速で40 cm/s以下であった.左右肺動脈への血流分布にも異常は認めなかった.Fontan循環全体におけるエネルギー損失(flow energy loss: FEL)は0.33 mWとごく低値であり,導管屈曲部での局所的な増加もほとんど認めなかった.ただし壁ずり応力(wall shear stress: WSS)は屈曲部で高値となっており,将来的に内膜増生に伴う狭窄の進行が懸念された(Fig. 4).
心室についての解析では右心室への拡張期流入血流は主に騎乗した僧帽弁からであり,三尖弁からの流入量は全体の10%程度であった.拡張期および収縮期に心室内に目立った乱流は認めなかった.流出路を持たない痕跡的左室を含めた解析ではEFは45%とやや低値であったが,CIは3.42 L/min/m2と十分なoutputを有していた.また心機能に対して痕跡的左室が与える影響について調べるため,心室間交通(ventricular septal defect: VSD)に着目した解析も行った.VSD通過血流に加速や乱流は認めず,収縮期には痕跡的左室から右室,そして大動脈に向けてスムーズに血液が駆出されている様子が観察された.さらには拡張期のVSD通過血流も左室から右室方向であり,僧帽弁通過血流の多くはそのまま右心室へ流入していることが明らかとなった(Fig. 5).心房,心室から大動脈,および心室内のみのFELは1.90 mW, 0.54 mWでいずれも低値であった(Fig. 6).
4D flow MRI結果をまとめると以下のようになる.TCPCの導管内での圧較差およびFELは低値であり導管の屈曲,狭窄はPLEの主な増悪因子ではない.ただし将来的に狭窄が進行していずれ交換が必要になる可能性がある.心室全体の駆出率はカテーテル検査での右室造影から算出されるより低値であったものの,十分なoutputを有する.また,心室機能において痕跡的左室が及ぼす悪影響は有意なものでなく,心室内での乱流やエネルギー損失も指摘されない.
これをふまえ,心室拡張末期圧上昇の原因について再度カテーテルでの右室圧曲線を分析し等容拡張期における圧曲線降下の時定数τを算出したところ,83 msと延長していたことから心室拡張障害の存在が示唆された.よって導管交換が必要となる前に,まずは心室拡張障害に対して,抗心不全療法としてβブロッカーを含む内科的治療を行い,PLE軽減およびステロイド減量を図る方針となった.
TCPC後の難治性PLE治療中に心外導管の屈曲が指摘され,導管交換を含めた治療方針の再検討に4D flow MRIが有用であったと考える.
TCPC後心外導管狭窄に対する再手術の適応については議論がある.現在一般的に用いられているePTFEグラフトを用いたTCPCにおいて導管狭窄の頻度は非常に低く,中野らも500例の心外導管TCPC術後中期成績において1例のみであったと報告している2).この1例は本症例と同様に術後の屈曲変形が最終的に石灰化を伴う著明な狭窄に発展し,再手術を要したとしている.一方でDacronを用いたTCPCでは内膜肥厚による導管の狭窄が高頻度で発生すると知られているが,Van Brakelらは再手術の適応を症候性の導管狭窄,もしくは無症候性であっても狭窄率が50%以上ある症例としている3).対象となったゼラチン処理DacronグラフトによるTCPC12例のうち8例が再手術となり,カテーテル検査での圧較差が1例は2 mmHg, 2例は1 mmHgで残りは圧較差を認めなかった上に狭窄度や症状の程度と圧較差に相関は認めなかったと報告している.
本症例の狭窄度はCTで計測した面積狭窄率で100−41.2=58.8%,カテーテルでの狭窄率は50%であり,難治性PLEを伴っており,Van Brakleらの基準によれば導管交換をすぐに行うという治療方針は妥当な方針となりうる.しかし実際には肺動脈圧も上昇しており,導管交換のみでは中心静脈圧の軽減を望むことは難しく,PLEの治療効果としては疑問が残ること,高用量ステロイド使用下での手術となることから再手術適応については慎重になる必要があり,詳細な血行動態評価のために4D flow MRIを要した.
4D flow MRIは3D cine phase contrast MRI(3次元シネ位相コントラストMRI)とも呼ばれ,phase contrast MRIを用いて得られた前後・左右・上下方向の速度分布を合成して時間分解能を持つ3次元の速度ベクトル分布を求め,これを積層したものである.3次元空間において血流を可視化できるだけでなく,任意断面を通過する血流量や心室等の容積,FELやWSSといった流体力学的パラメータが得られ,full volumeでの撮像の後で,後解析で自由に血行動態評価を行うことが可能である1, 4).その結果,血流の加速もなく,十分な血流量が低いエネルギー損失で導管を通過しており,導管屈曲は本症例においてFontan循環の血行動態を大きく妨げる現状には至っていない可能性が示唆された.ただし,屈曲部においてWSSが上昇していることが明らかとなり,このことは遠隔期には内膜へのストレスによる内皮増生を惹起する可能性を有しており5, 6)いずれ導管内狭窄による再手術が必要となる可能性を十分有していると考えらえた.
一方で,本症例は主心室の駆出が良好に保たれ,房室弁不全も軽度であったにもかかわらずEDPの上昇をきたしていた.単心室内の血行動態については,低形成な左室はVSD以外の流出路を持たないが流入路とある程度の容積を有しており,心室内血流の詳細や心室間相互作用を超音波検査やカテーテル検査で把握するのは容易ではなかった.心電図上のQRS幅が0.07秒であることに加えてSSFP法によるシネMRI上の3次元での心筋壁運動評価でも単心室としての主心室は左右心室にdyssynchronyはなく,また低形成左室からVSDを通じて右室流出路への血流は滑らかであり,右側房室弁からのinflowとの明らかな衝突や心内血流の乱流を認めなかった.収縮期での駆出血流はスムーズであり,心室内のFELは0.544 mWであった.この値の高低を評価するのは現在ではまだデータの蓄積が少ないため容易ではないが,例えば,主心室拍出仕事量をPressure Volume Loop(PV-Loop)内の面積として右室圧104/14 mmHg,心拍出量3.32 L/minという情報を基にPV-Loopを長方形で近似して算出される心室仕事量が663.9 mWとなることに鑑みると,本症例でのFELはごく低値であることがわかり,本症例での主心室内の血行動態そのものは異常とはいえなかった7).
しかし一方で,Fontan術後にはしばしば主心室の心筋機能として拡張障害が生じることが知られ,中でも弛緩障害は早期から認められ心筋肥大や慢性的虚血,弛緩期の心室の異常運動が原因とされる8).また特にGlenn手術前後で顕著な前負荷軽減が起こるが,前負荷の減少は心室壁厚の増大を引き起こし,心室コンプライアンス低下による拡張障害の原因となりうる9).本症例においても時定数τが延長していることから拡張障害,特に弛緩速度低下が指摘され,これがEDPおよびPA圧上昇の原因の1つと考えられた10).単心室例では組織ドプラ等を用いた心臓超音波での拡張障害の評価は極めて難しく,比較的若年の患者であるため抗心不全療法に関してはこれまで強化されずに経過観察されてきた経緯があったため,まずはそれを先行する方針となった.