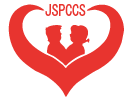小児循環器領域における植え込み型心臓電気デバイス治療適応
植え込み型心臓電気デバイスの適応となる病態には“徐脈”,“頻脈”,“心不全”がある1).この三つの病態を加味した上でデバイスを選択する必要がある(Fig. 1).ペースメーカが適応となるのは徐脈が主の病態で,心不全があっても心臓同期不全がみられない場合である.ICDを選択する場合は,徐脈の合併の有無にかかわらず,致死性頻拍の既往があるまたはそのリスクが高いと判断される場合である.心室同期不全を伴う心不全を認める場合はCRTを選択するが,CRT-Pが適応となるのは致死性頻拍のリスクが低いと判断される場合であり,CRT-Dは致死性頻拍の既往があるまたはそのリスクが高いと判断される場合である.
一般成人領域においては,CRT-Dの植え込み件数が増加しているが,小児循環器領域においては,未だペースメーカが主体である(Fig. 2A).これは,小児循環器領域では静脈アクセスが限られていること,ICD, CRT-P, CRT-Dのデバイス自体が成人・正常心血管構造患者用にデザインされており,小児・先天性心疾患に対応していないことが要因の一つとしてあげられる.
1. 経静脈心内膜アプローチvs.経胸壁心外膜アプローチ
ペースメーカ植え込みが適応となる体格の小さい小児では,経胸壁心外膜アプローチが選択される.心外膜リードは,年齢や疾患,リード留置部位が限定されないことが大きな利点であるが,植え込み侵襲が強く,リード寿命は心内膜リードより劣る1–3).心内膜リードでは成人領域10年で96.6~99.9%4),小児循環器領域では5年で84~89%5, 6)と報告されている一方,心外膜リードの累積リード不全回避率は5年で34~95%3, 5–10)である.近年,条件付きMRI対応機種が発売されているが,現在のところ心内膜リードのみの適応であり,心外膜リードはこれに対応していない.これらの利点・欠点を踏まえて経胸壁心外膜アプローチ(心外膜リード)を選択するか,経静脈心内膜アプローチ(心内膜リード)を選択するか決定する.心内膜リードの適応は施設により異なる.欧米では一般的に10~20 kg以上であるが11),思春期以降としている施設もある.新生児-乳児期早期に植え込んだ心内膜リードの良好な長期経過の報告もある12).しかしながら,心内膜リード植え込み後の静脈狭窄・閉塞は,一定の割合で発生する.成人では静脈狭窄は7~13%,閉塞は2~25%に発生し13),小児ではsingle chamber pacingで5%に鎖骨下静脈閉塞が確認された14).筆者はペースメーカを一生使用しなければならない小児の静脈を開存させておくことは重要で,心内膜リードの使用は思春期以降の適応が望ましいと考えている.
心外膜リードの耐久性が心内膜リードより劣ることはすでに述べたが,この原因の一つとして,患児の成長・発達の関与が考えられる.新生児期・乳児期で植え込まれた心外膜リードは身長が急激に伸びる思春期に断線を起こす場合がある.断線は突然みられるため,その予測はなかなか困難である.ペースメーカの適応となる疾患は様々であるが,心室補充調律がみられるか否かを確認し,補充調律がみられない,ペースメーカーリード断線で突然死を起こす可能性が高いと考えられる場合,乳児期早期に植え込まれたリードは思春期前に入れ替えを考慮すべきである.
2. ペースメーカ
ペースメーカの適応は小児おいても成人と同様で,徐脈による症状と心負荷の有無によって決定される.徐脈により致死的なイベントが起こる可能性があるもしくは,高率に心負荷の出現が予想される場合にも適応となる11).その適応のほとんどは房室ブロックであり,洞機能不全は少ない(Fig. 2B).最も多い疾患は先天性完全房室ブロックである.
先天性完全房室ブロックは,胎児期,新生児期早期に診断され,乳幼児期にペースメーカが植え込まれることが多い15, 16).この疾患群は経過中に拡張型心筋症を合併する場合があるが,心室ペーシングリード位置がその発症に関与している可能性がある.先天性完全房室ブロックに合併する拡張型心筋症および心不全死は,ペーシングリード留置部位が左室より右室心尖,右室流入路部に有意に高かった17).さらに,小児先天性完全房室ブロック178例の検討において,リード位置とポンプ機能・収縮効率・左室の同期性は関連し,右室収縮能は右室流出路・右室側壁ペーシングで低下し,左室心尖および左室側壁ペーシングで良好であった15).房室ブロックの合併に対する経胸壁心外膜アプローチの心室ペーシングリード留置部位は,左室心尖が第一選択で,右室自由壁は選択すべきではない18).
先天性完全房室ブロックでは,新生児期・乳児期早期には,完全房室ブロック時の房室同期不全の影響は少ないと一般的に考えられている11).心不全のない,新生児期・乳児期早期の患者には,まずsingle chamber pacingを植え込み,成長した後にdual chamber pacingに変更する19, 20).本邦,最小のペースメーカはsingle chamberであるが500円玉大であり,低出生体重児にも対応しうる(Fig. 3).
3. ICD
小児期にICDの適応となる疾患群のほとんどはQT延長症候群に代表されるチャネル病あるいは肥大型心筋症である21, 22).小児においても,不可逆的原因による致死性不整脈蘇生後の突然死二次予防はICDの絶対適応であるが,一次予防に関しては一定の見解はない.先人先天性心疾患を含む小児循環器領域のICD植え込み患者において約25%で適切作動がみられ23, 24),二次予防は一次予防と比較し,適切作動率が高かったと報告されている.
ICD植え込みに際して,小児特有の問題を考慮する必要がある.デバイスやリードのサイズが成人のものであること,成長とともに体格が変化すること,基本心拍数が速く洞性頻拍がよくみられること,活動性が高いことである.そのため不適切作動率が高く,リード不全,感染の合併症が起こりうる25).体重20~25 kg以上であれば,成人同様に経静脈心内膜アプローチでICDを植え込むことが可能であるが,それ以下の場合は工夫を要し11),これまで様々なショックリード留置方法が報告された1, 26–34).筆者は皮下にショックリードを留置し,上腹部にジェネレーターを植え込む方法を選択している.この方法は,比較的良好な除細動閾値と成功率が報告され,ショックリードの心外膜への癒着を防ぐことができショックリードの再植え込みも簡便である35, 36).しかし,リードの耐久性に問題があり,特にショックリードのdislodgementに注意を要する35, 36).
後述の完全皮下植込み型除細動器(S-ICD)は,成人を想定されてサイズが大きいこと(電池本体130 g, 59.5 cm3),出力エネルギーが一律80Jであることから,体格の小さな小児には適さない.小児の適応は25~30 kg以上とされるが,25 kg以下の植込み例の報告もある37, 38).
4. CRT-P/CRT-D
小児でCRT-D植え込み適応となる場合はごく稀であり,これまでの報告はCRT-Pが主体である.
小児循環器領域のCRT対象患者を過去のおおきな三つの報告でみてみると,三つの疾患群に分かれる.心筋症(9~17%),先天性完全房室ブロック(6~14%),先天性心疾患(71~80%)である39–41).小児では拡張型心筋症がCRTのnon-responderの独立した危険因子であったと報告40)されたが,これは小児の拡張型心筋症では,左脚ブロックを伴う典型的な左室同期不全を呈する例が少ないことが原因ではないかと推測する42).心筋症,先天性完全房室ブロック例は左室体心室疾患であり,経静脈心内膜アプローチであれ,経胸壁心外膜アプローチであれ,一般成人と同様に右室心尖とその対側・左室後側壁への留置43)が望ましい.小児においても,左室伝導遅延を伴う左室伝導遅延を伴う左室同期不全例には効果的であると考える.
1. 経静脈心内膜アプローチvs.経胸壁心外膜アプローチ
CHD患者では,ペースメーカを植え込む際,体格のみならず,静脈アクセスやその解剖を理解する必要がある.まず,手術侵襲の低い経静脈心内膜アプローチが可能であるかどうか検討する.鎖骨下静脈が閉塞している場合,左上大静脈遺残が存在したり,Fontan術後のように上大静脈が心房に結合していない場合,心房内血流転換術後の心房内に狭窄が存在する場合がある.過去に手術既往がある場合は静脈造影で,静脈閉塞の有無を確認する.また強い三尖弁逆流により,右室にリードが留置困難な場合もある.静脈アクセスが確保できても,心内短絡がある場合は奇異塞栓を起こす可能性があり,心内膜リードは使用すべきではない44).2014年the Pediatric and Congenital Electrophysiology Society(PACES)/the Heart Rhythm Society(HRS)から出されたExpert consensus statement45)では,心内短絡がある場合の心内膜リードの植え込みはクラスIIIに位置づけられ,血行動態・抗凝固療法の導入・シャント閉鎖の有無・心内膜リードの代わりとなるリードアクセスを個々に検討し決定することとされている.
経静脈心内膜アプローチが適さない場合には経胸壁心外膜アプローチを選択するが,過去の手術の切開線,癒着の程度,手術侵襲に耐えられる血行動態であるかを十分検討する.
2. ペースメーカ
1)適応
(1)先天的に解剖学的な刺激伝導系の異常に伴う徐脈,(2)術後合併症としての徐脈,(3)心房負荷による心房性頻拍の合併と潜在的な洞不全症候群の三つに分けられる.
(1)先天的に解剖学的な刺激伝導系の異常に伴う徐脈
代表される疾患は,房室錯位と,左側相同心である.
房室錯位では,心房中隔と心室中隔の整列状態により,発生過程の前後房室結節のうち,後方結節だけ残る場合,前方結節だけ残る場合,前後両方の房室結節(Twin AV node)が残る場合がある46, 47).後方房室結節はKochの三角に存在するべきもので,前方房室結節は僧房弁弁輪の肺動脈が接する位置に存在し,下部刺激伝導路は肺動脈前方を通り心室中隔に延びる.このような房室間刺激伝導路の解剖異常をもつ房室錯位では,自然発生的に加齢とともに房室ブロックが起こる.近年は手術介入もあり,その自然予後をみるのは難しく,最も代表的な報告は1983年のもので,107人の患者のうち23人に房室ブロックが自然経過で発生し,その発生率は1年に2%であった48).さらに,38例と少数例であるが,心房正位と逆位を比較し,逆位では房室ブロックが少ないとの報告がある49).その理由として,逆位では心房中隔と心室中隔が整列しており,後方房室間刺激伝導が優位であることの関連性が疑われている.
左側相同心での剖検所見では,洞結節が存在する分界稜は,88%で両側心房共に存在しなかった50).さらに洞結節は左側相同心では洞結節が44%で低形性で,56%で無形性であった51).房室結節は一つまたは二つ存在するが,52%で下部刺激伝導系との連続性がなかった51).このため,洞機能不全,房室ブロックの合併が多い52, 53).特に洞機能不全の合併は加齢とともに増加し,40歳でその累積回避率は13%であった53).
これらの先天的な刺激伝導系の異常をもつ疾患群に,いつペースメーカを植え込むかはまだまだ議論の余地が残る.無症状であっても,ホルター心電図や運動負荷心電図を定期的に行って徐脈の進行の有無を把握し,徐脈による心負荷が進行する前に,ペースメーカ植え込みを考慮すべきである.
(2)術後合併症としての徐脈
最も多い徐脈は房室ブロックである.CHD術後の完全房室ブロックは予後不良であることが知られており54),回復する見込みのない高度,もしくは完全房室ブロックはペースメーカの絶対的適応である.術後の一過性房室ブロックの回復期は周術期9~10日以内がほとんどであるが,それ以降の場合もある55, 56).しかし,周術期一過性房室ブロックは,数年もしくは数十年後に完全房室ブロックに進行する場合があり,突然死のリスクがある56–59).周術期一過性房室ブロックの遠隔期にみられる突然死は,回復期間との関与はないとする報告もあるが56),術後3日以上のものを危険因子とする報告もある58, 59).いずれにしろ,術後房室ブロックは一過性であってもその後も注意深い観察を要する.
(3)心房負荷による心房性頻拍の合併と潜在的な洞不全症候群
Fontan術後,心房内血流転換術後や未修復チアノーゼ性心疾患等,右房負荷がみられるあらゆる疾患群がこれにあたる.
最も代表的であるのは,古典的Fontan手術,心房肺動脈吻合型(atriopulmonary connection; APC)である.右房に圧負荷,容量負荷がかかり,洞機能不全,心房性頻拍が高率に発生する60, 61).上下大静脈吻合型(Total cavopulmonary connection; TCPC)であっても術後年数が経過するとともに心房性頻拍の発症率が増加する61, 62).Fontan術後遠隔期の心房頻拍の発生は,年齢と右房の著明な拡大,線維化と関与しており63),抗不整脈薬投与により潜在的な洞機能不全が出現する場合がある.
心房内血流転換術(Mustard・Senning手術)においても高率に洞機能不全や心房性頻拍を合併し,術後経過年数とともにその発症率は増加する.術後20年での洞機能不全回避率はMustard手術で46%, Senning手術で40%であった64).
CHD術後遠隔期における洞機能不全と心房頻拍は密接に関与しており,心房頻拍に対して抗不整脈薬を投与することにより,洞機能不全が明らかになることがある.心房頻拍に洞機能不全の合併がみられた際にはペースメーカ植え込みを考慮する.
2)ペースメーカ設定(Fig. 4)
ペースメーカ設定は血行動態に大きく影響する.ペースメーカ植え込み後にはまず,至適なlower rateの設定が必要であるが,解剖・血行動態により変化し,標準となりうる設定方法はない.右室不全を合併し,静脈圧が高いような病態では中心静脈圧をモニタリングしながら,lower rateを決定する.ホルター心電図や運動負荷心電図で,活動時の心拍上昇を確認できない場合はrate response機能を使用する.心室ペーシングにより,心室同期不全を引き起こし心機能不全を発症することがあるので,できるだけ自己房室伝導を活かすような設定を心がける.I度房室ブロックの場合にはatrioventricular intervalをできるだけ延長する.自己QRSが脱落したときにのみ,single chamber pacingからdual chamber pacingに自動で切り替わる機能が各社のペースメーカに搭載されており,これも有用である.
高い心室ペーシング率を避けることができない場合は,至適なatrioventricular intervalの設定を要する.心不全患者においては,心拍出量の20~30%は心房収縮によるものであり,房室同期不全は心拍出量の低下,収縮期血圧の低下をきたす65, 66).至適なatrioventricular intervalの設定には,いろいろな方法があるが,複雑な解剖をもつ先天性疾患では心エコーでの設定が有用で,房室流入血流のA波の終末が房室弁閉鎖点に一致するように設定する65, 67, 68).
3. ICD
1)適応
CHDで小児期にICDの適応となる致死性不整脈を合併する例は稀で,成人期に出現することが多い.CHDにおいても,不可逆的原因による致死性不整脈蘇生後の突然死二次予防はICD絶対適応である69).しかし,心臓突然死一次予防については,疾患が多岐にわたっており,心臓突然死の危険因子を検討する無作為臨床試験はなく,未だ確立された適応はない70).
なかでも最も詳細に検討されているのはFallot四徴術後である.肺動脈弁逆流による右室容量負荷が致死性不整脈発生の主要な病態とされ,180 ms以上のQRS幅や右室機能不全が危険因子とされてきたが71, 72),これに加え左室拡張末期圧上昇などの左室の指標も重要とする報告が近年,散見される73–75).
電気生理検査の有用性は疾患によって異なる.Fallot四徴術後では,電気生理検査での心室性頻拍誘発がICD適正作動の予測に有用であった76).完全大血管転位心房内血流転換術後では,17人に心室頻拍誘発試験を行った後ICDを植え込んだ報告があり,ICDの適切作動がみられたのは心室頻拍が誘発されなかった3人のみであった77).この結果から完全大血管転位心房内血流転換術後には,心室性頻拍誘発試験は心臓突然死の予測に有用でないとされている.これはFallot四徴術後の心室頻拍の多くは右室切開線に関与して起こるのに対して,完全大血管転位心房内血流転換術後は心室切開を施行していないことが多く,致死性頻拍性不整脈の機序がFallot四徴術後とは異なるためであろう.興味深いことに,完全大血管転位心房内血流転換術後のICD植え込み後の適切作動例の50%に,心房性頻拍が心室頻拍に移行または同時に存在しているのが記録されたと報告されている77).
2)ICD植え込み
静脈アクセスが制限されて入る場合,心内シャントが残存している場合には,ショックリードの植え込み方法に工夫を要する.これまで,小児と同様な植え込み方法が報告されている(Fig. 3).徐脈を合併していない場合にはS-ICDが有用である.
3)完全皮下植え込み型除細動器(S-ICD)
通常のICDとは異なり,心内膜側や心外膜側にリードを留置せず,ショックリードを皮下に,デバイス本体を腋窩に植え込む(Fig. 5)78).2016年2月より本邦でも使用可能となり,条件付きでMRI撮像も可能である.皮下にのみリードを留置するため,静脈アクセスが限定されているCHD患者にも使用でき,開胸を必要としないため植え込み侵襲も小さい.電気ショック時の心筋障害は心内膜ショックリードと比較し小さい.しかし,センシングは皮下リードで行われるためセンシング不良が起こりやすく,徐脈に対するペーシング機能を備えていない.また,成人用に製造されており,デバイス本体は130 g,59.5 cm3とかなり大きく,皮下リードも成人の体格を想定してデザインされている.出力エネルギーは一律80Jである.先天性疾患に対する長期的な報告32)は十分ではなく,今後,症例の蓄積が待たれる.
4. CRT-P/CRT-D
CHDにおいてもCRT-D植え込み適応となる場合はごく稀であり,これまでの報告はCRT-Pが主体である.
CHD患者のCRTの適応はいまだ確立されたものはない.これまでのところ,最も明瞭にその適応について記載されているのは2014年の成人先天性心疾患のExpert consensus statement69)である.ここではCHD患者を二心室体心室左室,二心室体心室右室,単心室血行動態と大きく三つにわけて議論されている.体心室左室においては成人領域での適応がそのまま用いられている.二心室体心室右室や,単心室血行動態においても体心室駆出率の低下と体心室脚ブロックを伴うQRS幅の増大がその適応としてあげられているが,Class IIaであり,Class Iの適応はない.私見ではあるが,体心室形態にかかわらず,心室同期不全があって,それが原因の心機能低下が認められるなら,CRTを積極的に導入すべきであると考える.心室同期不全の有無については,安静時12誘導心電図におけるQRS幅や電気生理検査での心内心電図で電気的同期不全を判断し,心エコーや心室造影で機械的同期不全を判断する79, 80).これらをもとに行う,カテーテル検査室でのCRT急性効果判定試験はCRT適応判断の助けになりうる79–81).
CRTの適応となるCHDでは,成人領域とは異なる心室同期不全を呈する特殊な心室形態(単心室血行動態と右室体心室)を理解しておく必要がある.単心室血行動態を呈する心室形態では,主となる体心室の他に痕跡的な心室を有し,大きな心室中隔欠損が二つの心室間に存在することが多い.この二つの心室間に収縮のずれが生じると,心室中隔欠損を血流がswingingして,なかなか前方に拍出されない“biventricular swinging motion”が生じる80).これは単心室血行動態にみられる特殊な心室同期不全であり,この改善には両心室が同時に収縮できるリード位置を選択する1).
右室体心室は,単心室血行動態,二心室血行動態どちらの場合も存在するが,右室長軸方向同期不全80)を認める場合がある.右室長軸方向同期不全は,右室心尖から極端に遅れて右室流出路が収縮する右室内同期不全である.この場合は右室を長軸方向にはさむような位置にリードを留置すべきである.さらに二心室血行動態を呈する右室体心室では,心室間同期不全79)が心室内同期不全より血行動態に大きく影響している場合がある.右室体心室疾患においては,右室長軸方向同期不全,心室間同期不全どちらもカバーできるリード位置は左室と右室流出路である1).
CHDのCRTを行う際には,至適リード位置,手術侵襲,解剖を加味して植え込み方法を決定してゆく.