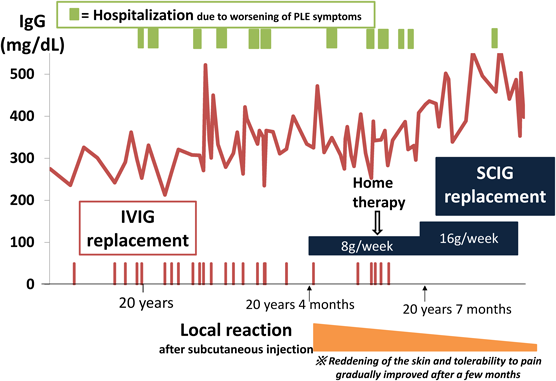TCPC術後の蛋白漏出性胃腸症に伴う低IgG血症に対し,pH 4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)による在宅補充療法を導入した1例Subcutaneous Immunoglobulin (SCIG) Home Therapy for Treatment of Hypogammaglobulinemia due to Protein-losing Enteropathy (PLE) after Total Cavopulmonary Connection
1 大垣市民病院小児循環器新生児科Department of Pediatric Cardiology and Neonatology, Ogaki Municipal Hospital ◇ Gifu, Japan
2 愛知県済生会リハビリテーション病院Aichi Saiseikai Rehabilitation Hospital ◇ Aichi, Japan