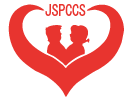心室中隔欠損閉鎖に用いるパッチ幅を基準化した完全型房室中隔欠損修復術Surgical Correction of Complete Atrioventricular Septal Defects with Standardized Sized Ventricular Septal Defect Patch Width
1 大阪府立母子保健総合医療センター小児医療部門心臓血管外科Department of Cardiovascular Surgery, Chidren's Hospital, Osaka Medical Center and Research Institute for Maternal and Child Health ◇ 〒594-1101 大阪府和泉市室堂町840番地840 Murodo-cho, Izumi-shi, Osaka 594-1101, Japan
2 大阪府立母子保健総合医療センター小児医療部門小児循環器科Department of Pediatric Cardiology, Chidren's Hospital, Osaka Medical Center and Research Institute for Maternal and Child Health ◇ 〒594-1101 大阪府和泉市室堂町840番地840 Murodo-cho, Izumi-shi, Osaka 594-1101, Japan